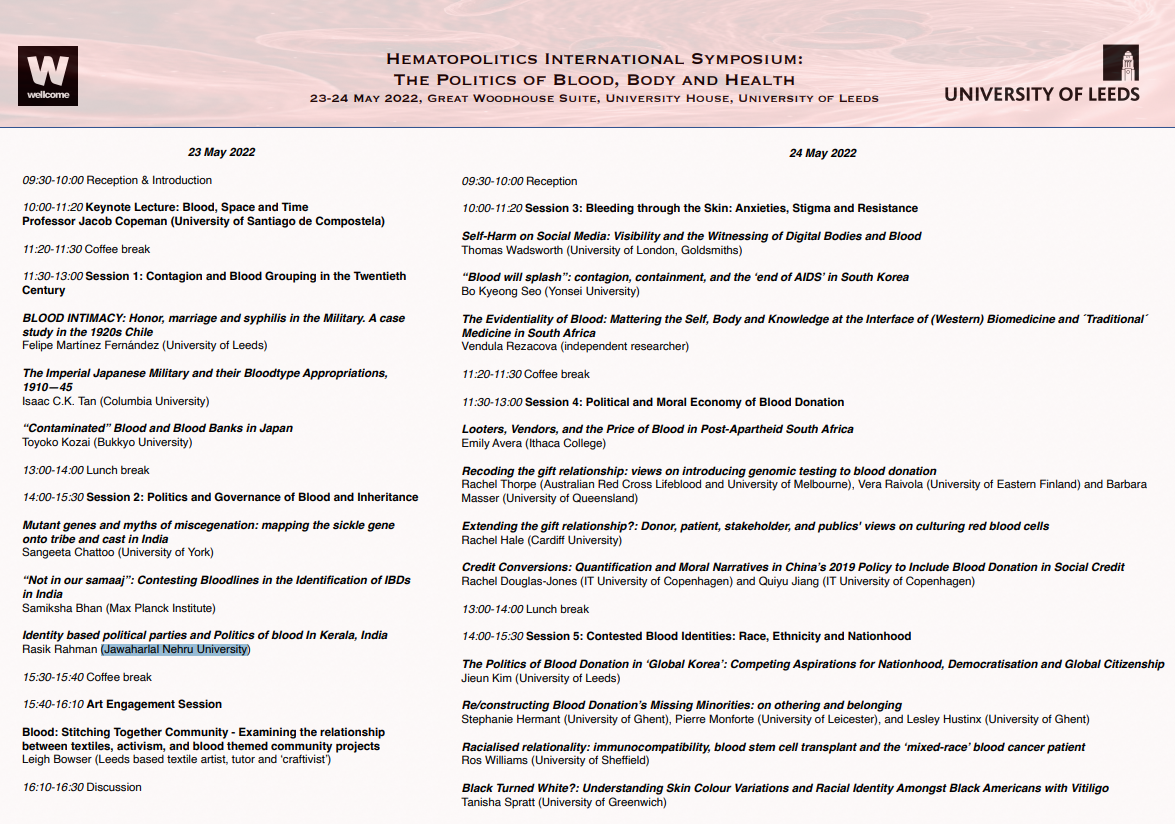この夏、私はブラッド・バッグ・プロジェクトの創始者であるリー・バウザーと共に、ソウルと京都でテキスタイル・ブラッド・バッグ作りのワークショップを開催した。リーは、ダイヤモンド黒色貧血という稀な血液疾患に苦しむ姪のクロエを支援するために、このプロジェクトを立ち上げた。2021年にリーの作品に出会った私は、血液をめぐる対話とつながりを生み出すリーの工芸品使いに魅了された。リーのテキスタイルの血液バッグは、作り手の意図と相互のつながりを具体化し、生物医学的な血液バッグの回路と並行して独自の回路を作り出していた。それ以来、私はリーをヘマトポリティクス・シンポジウムに招いて講演してもらい、地元の小学校で6年生を対象としたワークショップを共催した。これらの経験から、韓国と日本の私のフィールドで、献血者、患者、支援者を結びつける血液バッグ・ワークショップの可能性について考えるようになった。ソウル(韓国白血病患者団体)と京都(佛教大学光西豊子教授)の協力者と調整し、それぞれの機会に合わせてプログラムを作り直し、両地域でワークショップを共催することができた。リーにとって、英国以外で血液バッグのワークショップを開催するのは初めてのことだった。以下は、その出会いについてのリーの考察である(Jieun Kim)。
旅行の前に
ソウルと京都に行く前に、ジニ(Dr. Jieun Kim)と私は、参加者にとってできるだけ有益な情報をまとめることに努めた。これには、ワークショップのスケジュールも含まれ、参加者がバッグ作りに必要な時間を十分に確保できるよう、時間を区切って説明した。入手可能な材料の写真や他のバッグの見本は、参加者にインスピレーションを与えるのに役立った。ジニは事前にこれらを韓国語と日本語に翻訳した。
私たちは、作り手が好きな文章を入れられる特別なラベルがあれば便利だということに同意した。また、それぞれのバッグを誰が作ったのか、どの工房で作られたのかを記録する手段にもなる。私たちは、血液バッグに貼られているステッカーを模倣し、名前、場所、真正性を示す偽のバーコードが入ったラベルを作ることで合意した。一緒にデザインを考えた後、リーズ・プリント・ワークショップで印刷用スクリーンを作り、個々のラベルをキャラコに手刷りした。乾いてから熱プレスし、私のオーバーロッカーミシンを使って手作業でオーバーロックした。印刷の過程でも、また参加者が何を入れたいか考えを変えるかもしれないので、失敗を許容するために、全部で40枚のラベルを作った。
言葉の壁があってもワークショップができるだけ自然に進行するように、私はステッチを使ったワークショップでよく受ける質問(例えば、針に糸を通すのを手伝ってもらえますか)をミニ質問カードにまとめた。ジニの助けを借りて、これを韓国語と日本語に翻訳し、両面印刷した。各参加者に配られるインフォメーション・パックの中に入れた。
言葉の壁は少し緊張するかもしれませんが、10年以上ステッチを使ったワークショップで人々と関わってきた経験から、それほど混乱することなく人々をサポートできると確信していました。これまでの経験から、ステッチをするときの人々のボディランゲージや創作プロセスのパターンを理解し、彼らが苦戦しているときや助けを必要としているときを読み取ることができるようになりました。物理的な作業なので、技術がどのように達成されるかを示すために、言葉を使わずにデモを使うことができる(例えば、ステッチのやり方を言葉で説明するのではなく、物理的に示すことができる簡単なステップに分解することができる)。
ブラッドバッグクラフトワークショップ – ソウル – 2020日2024年7月20日
ワークショップの会場に着くと、このワークショップのために作られた大きな立看板が迎えてくれた。明るくはっきりしたグラフィックで、文字を翻訳する前に、何のためにあるのかがよくわかった。この看板を作るために費やされた労力と印刷代は、このワークショップを企画した人たちが多くの努力をし、このワークショップに熱意を注いでいることを意味している。

スペースに入ると、KLPO(韓国白血病患者団体)のチーム、安基鍾(アン・ギジョン)さんと李恩永(イ・ウンヨン)さん、そして素敵なボランティアさんたちが私を迎えてくれ、リラックスさせてくれた。私たちは一緒に準備をし、資料や機材、書類を並べ、プレゼンテーションのスクリーンを設置した。ジニは、誰が参加するのか、ワークショップの大まかな流れを話してくれた。スケジュールは事前に予習していたが、改めて確認することができて心強かった。
参加者が到着し(17人ほど)、あらかじめ用意された席に座り始めた。KLPOは、小さな子ども連れの家族を一緒に座らせるなど、参加者同士がつながりやすいように配慮した。これは、KLPOのイベントに初めて参加し、それぞれ一人で来ていた3人の若者には特に効果的だった。この共通の体験は、彼らの絆を深めるのに十分だった。ワークショップを通して、彼らは少しずつお互いを知り、音楽などの共通の興味を持つようになった。
ほとんどのゲストが到着したところで、イ・ウンヨンがワークショップの紹介をし、彼女の実体験、特にKLPOを立ち上げた理由を語った。続いてマイクが回され、参加者が自己紹介と白血病にまつわるエピソードを披露した。ジニさんは、これらの体験談を私に通訳してくれた。多くの参加者にとって、このワークショップはKLPOのイベントに参加するのも、自分と同じような経験(白血病の治療を経験したり、家族をサポートしたり)を持つ人たちに会うのも初めてのことだった。多くの人が、参加することに緊張していたものの、他の人たちとのつながりができることを楽しみにしていたという。自分自身や幼い子どもの治療で大変だったことを話す人もいたが、グループの他のメンバーはそれを理解し、共感してくれた。自分の体験談を話してくれたすべての人に感謝している。
一緒に座っていた3人の若者のうちの1人、チョウは、自分の話をすることに最も自信を持っているように見えた。彼は、バッグの中央にある同じハートにたくさんの手が触れているデザインにとても熱中していた。これは、献血をしてくれた人たちを含め、治療を通して彼を助けてくれたさまざまな人たちを象徴するものだった。彼は裁縫の技術に少し自信がなかったが、自分の作品に興奮し、満足のいく形に仕上げることができた。その熱意を周りの人たちにも伝えるのが上手で、みんなを集めて写真を撮ったり、自分のバッグを披露するように促したりしていた。ワークショップの間、チョーはKLPOがみんなをひとつにまとめてくれたことに感謝の意を表した。彼のオープンでフレンドリーで熱心な参加にとても感謝している。チョウは自身の体験をソーシャルメディアでシェアした: https://www.instagram.com/p/C9pPCY1z3Ks/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
事前に作成された翻訳カードは、ワークショップ中に非常に役に立ち、参加者のニーズを理解するのに役立ちました。. I also try to pre-empt que 人が作業しているのを見ることで、その人の疑問を解決することができる。例えば、針に糸を通そうとしている人がいたら、手助けをする前に、その人自身に何度か挑戦させてみる。ボランティアはまた、ワークショップの間中、参加者と私をサポートしてくれた。私が他の人のサポートをしている間に誰かがサポートを必要とした場合、彼らはまず最善を尽くして助けようとし、その後、継続的なサポートが必要かどうか私に直接尋ねてきた。これは、コミュニケーション・カードを通して口頭で、また針や糸を持ち上げるような理解しやすい手振りをすることによって行われた。
6歳と8歳の2人の子どもたちと一緒に作業したとき、物理的な、直接会って行うワークショップの利点が最もよくわかった。ふたりとも裁縫の経験はなく、英語も話せなかった(私の韓国語はハローとサンキューが精一杯!)。しかし、バッグの作り方をステップ・バイ・ステップで教えることで、2人とも絵を描き、裁断し、自分のアイデアを縫い合わせることができた。二人ともとても忍耐強く、断固とした態度だった。

家族で協力して、それぞれの経験を反映させた1つのバッグを制作した人もいた。イギリスや韓国を含め、世界中の子どもたちに愛されているヒーロー、ミラクルてんとう虫のデザインに取り組んだ母子もいた。このよく知られたキャラクターは、そのキャラクターのファンであればすぐに作品と結びつくため、言葉によるコミュニケーションを必要とせずに世界的なつながりができることを示すもうひとつの例である。ある家族は、病院を訪れ、治療や経験によって同年代の子どもたちから孤立していた子どもの「友達」になった青いキャラクターを使った。このキュートでかわいいキャラクターは、子どもたちを幸せな気分にさせ、その姿を見るのが大好きだった。時には怖い経験も、柔らかく、かわいらしく、愛すべきものにキャラクター化することで、人々は、特に幼い子供たちは、対処することができる。このことは、クロエの物語を私自身が語ることで調査したことであり、ジニと私は今後さらに調査していくつもりである。
ワークショップの数日後、私はエキサイティングなビデオや記事へのリンクを3つ受け取った。そのうちのひとつは、参加者のキム・ダンヨンから直接送られてきたものだ:
https://youtu.be/3NCE04eeAv4?si=1AUQkuKThrhokcCo
キム・ダンヨンは病気になる前、熱心なクラフト作家でありYoutuberだった。彼女は過酷な白血病の治療中に四肢を失い、その日のワークショップをきっかけに手芸のチャンネルを再開したと話してくれた。彼女のYouTubeには、新しい手への愛と、時には夫の特別なサポートを受けながら、手芸を含めてまだできることが紹介されている。今回もまた、キム・ダンヨンがその過程とイベントを記録することを予期し、先回りして考えてくれたことで、私は彼女にとってのこのイベントの重要性を理解することができた。当日、私たちと分かち合ってくれただけでなく、彼女のソーシャルメディアを通してこのことをシェアし続けてくれたキム・ダンヨンには、とても感謝している。
同じことがKLPOにも言える。KLPOは、ワークショップの様子を撮影するために、ビデオグラファーとカメラマーをイベントに参加させていた:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=kIJqYTGzRLs&feature=youtu.be
最後にジニと私自身にインタビューが行われ、どうだったか振り返ることができた。この映像は、プロジェクトとジニの研究を紹介するYouTubeのビデオとして使用された。韓国でのワークショップは、英国で開催しているワークショップと違っていたかと尋ねられたが、文化的な違いは感じなかったし、言葉の壁がワークショップを最高のものにする妨げになっていたとも思わなかった。最大の違いは、参加者自身だった。彼らの実体験が、ワークショップをより共感的で理解のある場にし、困難な医療体験を共有することで、人々がより深くつながることを可能にしたのだ。
この日は韓国の医療サイト『Hit News』でも紹介された:
http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=56277
ブラッドバッグクラフトワークショップ – 京都 – 3第3回2024年8月3日
回目のワークショップは、佛教大学二条キャンパスで開催され、古在教授の協力を得てまとめられた。古在教授はこのワークショップに参加する学生や友人を募り、その中には献血に関係のある人もいたが、そうでない人も多かった。準備の後、8人の参加者が到着し、自己紹介が行われた。ほとんどの学生が、参加した理由を「教授を尊敬しており、新しいことを学びたかったから」と語った。ある学生は、友人が定期的に輸血を受けなければならなかったので、その影響を受けて、もっと学ぶために参加したと語った。刺繍のような新しい技術を学びたい、ダイヤモンド黒色貧血や献血についてもっと知りたい、輸血を受けたことのある人を知っているから参加する、などである。

参加者たちがデザインを作り始めると、作り手たちに共通するテーマは、希望と喜びを広めたいということだった。ここでもまた、キャラクターや性格付けがその方法となった。図形に笑顔を加えることで、陽気な個性を与えることができた。ハートや手も、両ワークショップで大きく取り上げられた。このアイコンは、人と人とのつながり、愛、幸福のシンボルとして、ほとんどの文化にまたがっている。

私はこのワークショップを楽しんで行ったが、参加者はソウルのときよりも少し不安そうだった。これはワークショップでは珍しいことではなく、参加者がそのトピックに個人的なつながりがないと、共通の話題を見つけるのが難しくなる。また、不慣れな人たちと仕事をするという緊張感も、参加者を少しためらわせる。とはいえ、この日は全員がテキスタイル作品を完成させようと懸命に取り組んだ。最年少の9~11歳くらいのメンバー2人は、自分のアイデアに最も自信を持っているようで、プロジェクトについて最もオープンに話してくれた。ブラッド・バッグ・プロジェクト』で子どもたちと一緒に仕事をする中で、子どもたちが若ければ若いほど、自分のアイデアに自信を持ち、「これでいいのか」という心配をあまりせず、自分の創作に没頭できることがわかった。クリエイティブな分野で働かない限り、大人は普段からクリエイティブに自由になる「許可」をあまり与えられていないことが多い。
全体的な振り返り
この経験全体が、私の記憶に残り、長い間感謝することになるだろう。特にソウルのワークショップでは、オープンで正直で、傷つきやすい体験談を分かち合うことができた。ブラッドバッグをベースにしたワークショップのほとんどは、京都のワークショップと似たようなものですが(つまり、人々が献血や輸血を受ける理由について学ぶというものです)、KLPOのワークショップでは、患者グループと直接関わることの重要性を身をもって学びました。工芸を通して人々とつながることができることが、私がこの仕事を愛する理由です。他の言語を話し、私とは異なる経験を持つ人たちと一緒にこの仕事をすることで、工芸、特にこの場合はテキスタイルが、さまざまな障壁にもかかわらず人々をつなぐことができることを身をもって証明することができたからです(著者:Leigh Bowser)。